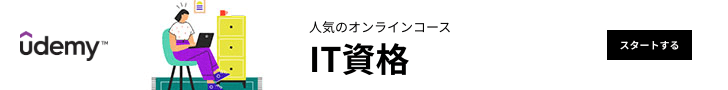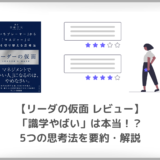インフラ苦手意識のある30代エンジニアが、AWSアソシエイトレベルの3資格を半年間で受験。
AWSを勉強したことで、インフラに対する意識が変わり始めています。
この記事では、AWS勉強による変化やメリットを紹介していきます。
初心者アプリエンジニアがAWSを勉強した背景
クラウドインフラサービスは昨今どの企業でも導入され始めています。
Amazonがサービス展開するAWS。Googleが展開するGoogle Cloud Platform。
インフラエンジニアだけでなく、アプリケーションエンジニアもインフラ環境についての理解を深める必要も出てきています。
なぜなら、運用フェーズでもアプリケーションエンジニアに責任がついてまわるからです。
このままではまずいと思い、AWS勉強を決めました。
初心者アプリエンジニアがAWSを勉強するメリット
AWSを勉強するメリットは、インフラに対する苦手意識を払拭することができることです。
苦手意識は、「知識不足」からくるもので、サービスの概要を勉強することで、苦手意識を減らすことが出来ます。
- AWSサービスを理解することでインフラ苦手意識が弱まる
- サービス連携について理解が深まり、自システムの理解が更に深まる
- アプリケーションエンジニアとしての幅が広がる(できることが増える)
実際に勉強前と勉強後の変化を事象でお話します。
AWSを勉強したことによる変化
勉強開始前と開始後の変化は以下です。
| 変化 | AWS勉強前 | AWS勉強後 |
|---|---|---|
| インフラに対する意識 | インフラと聞くだけでちょっと無理… | そのサービス聞いたことある!こういうインフラ構築もできるのか! |
| インフラチームとの業務 | インフラチームの要求が分からない… | 要求について理解!ちょっと調べた後回答します! |
| システム設計 | インフラ設計はわからん… | システム要件はこうだから、この構成にすればよいのかな? |
| システム実装 | アプリケーションが動けば良し! | アプリケーションはローカルで動いた! サーバに設置して動かすから、これとこれを用意しよう |
| システム運用 (障害対応) | 何かが起きてるらしい… | CloudWatch見てみよう。 アプリケーション側でできることはあまりないな。 ここをスケールアップすればよい? |
AWS勉強後、あきらかな変化があり、業務でできることが増えました。
そして、何よりも「AWSわかるって楽しい!」
AWS学習ステップ|勉強方法の紹介
インフラ苦手意識を持つ30代のアプリケーションエンジニアが、約半年間で3つの資格を受験しました。
おすすめ度と合わせてステップごとに紹介します。
AWSサービスを理解する方法として、AWS試験の黒本購読とUdemyの動画講義をおすすめします。
全体的なイメージを掴むためには、黒本で主要なサービスを理解できます。
誰もが触る可能性のある主要サービスを抑えているので、AWS全然使ったことないという方には手っ取り早いです。
AWSを知っていて、理解したい内容がイメージできている方は、Udemyの動画講義で目的にあった動画を見ることをおすすめします。
目的別に様々な動画コンテンツが用意されているので、知りたい情報が見つけられるはずです。
この試験を勉強することで、各主要サービスのベストプラクティスとベストなサービス連携が分かります。
SAAについて詳しく知りたい方はこちらの、AWS SAA合格体験記をご覧ください。
ただし、DVA自体は、非常にニッチな内容(例:〇〇が使うconfファイル名)なので、あまり持ってても役立たないかもと思います。
なので、システム開発者の方は、開発時に扱うサービスを深堀りするほうが良いかもです。
DVAについて詳しく知りたい方はこちらのAWS DVA合格体験記をご覧ください。
コンソール画面を使ってサービス開発をするラボ試験も導入されて、より実践的な試験になりました。
ラボ試験対策で利用した、AWS初心者ハンズオンは1番おすすめ★★★★★です!!
要件に合わせたAWSサービス設計を解説してくれて、コンソールを使いハンズオン形式で説明してくれています。
このハンズオンを全部見るだけでも、かなりAWSについて理解を深めることができます。
SOAについて詳しく知りたい方はこちらの AWS SOA落ちた|不合格体験記をご覧ください。
ステップ1で紹介したAWS黒本はこちらです。(最新:2021/01/08)
AWS初学者は、この黒本とステップ4で紹介したハンズオンを一通り実践することでかなり理解が深められると思います。
ステップ1で紹介したUdemyは以下の画像リンクからサイトに飛びます。
AWSの動画講義は数多く紹介されているので、目的にあった動画に出会えるはず。
資格試験勉強を通じて、更に知識を詰め込んでいきましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
AWSの勉強をすることでのメリットや初学者向けのAWS勉強方法を理解していただけたと思います。
アソシエイト資格試験に挑戦したいという方は、こちらの30代エンジニアのAWSアソシエイト資格に挑戦もご覧ください。
最後までご覧頂きありがとうございました!
一緒にAWSを勉強して、楽しいエンジニアライフを贈りましょう!